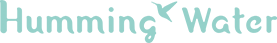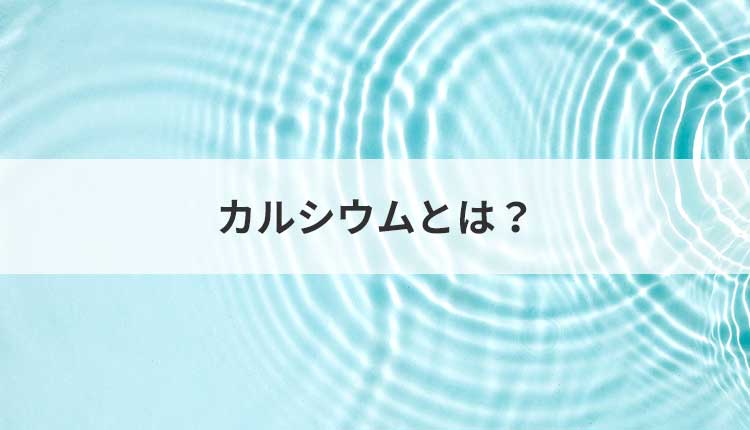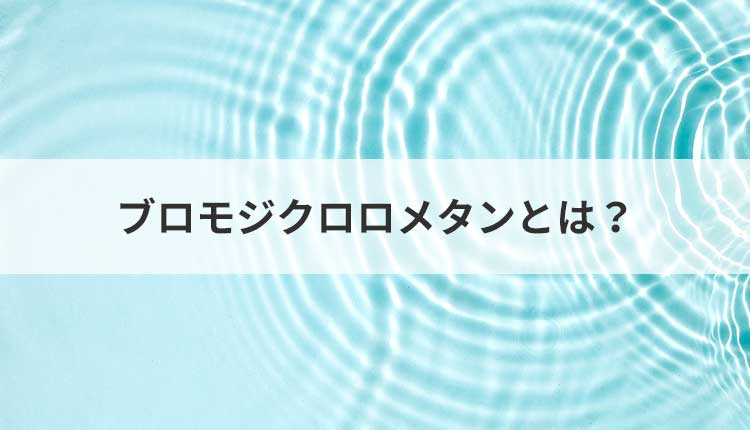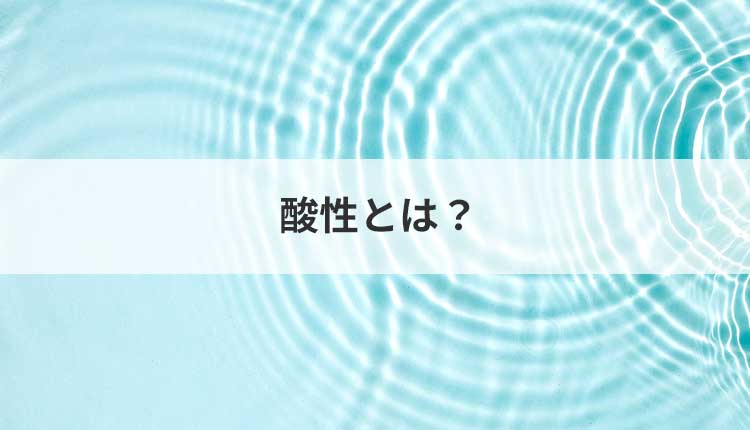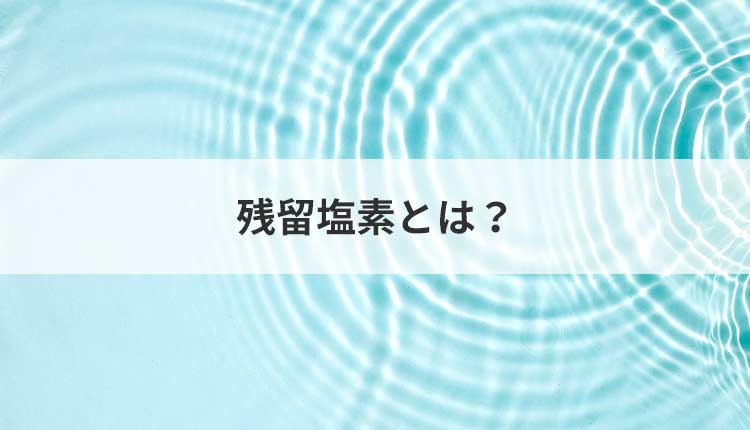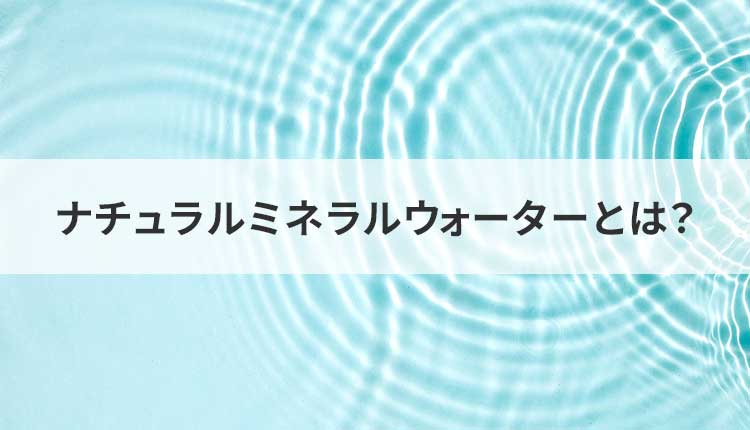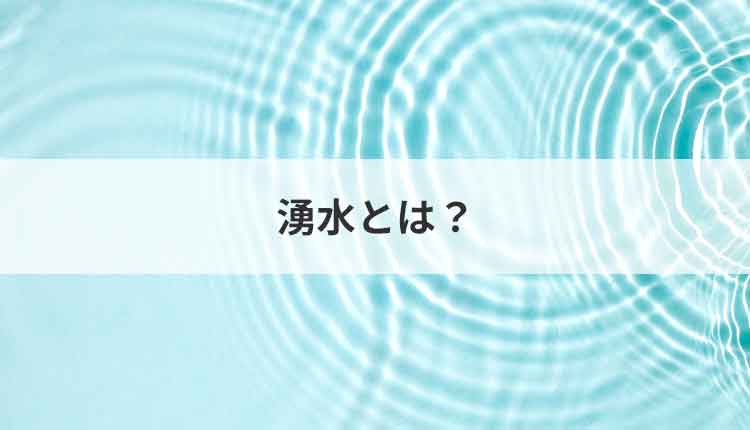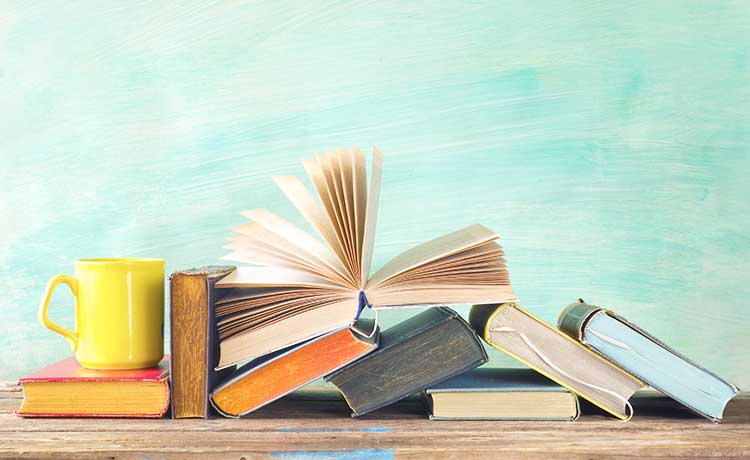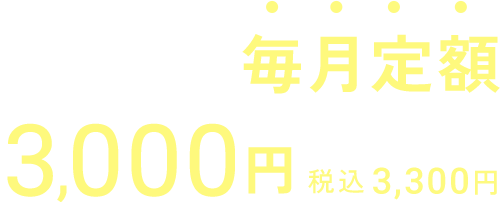カルシウムとは?
カルシウムは体重の1〜2%程度含まれているミネラルで、ミネラルとしては生体内で最も多く存在します。その大部分は骨や歯に存在し、ほんの少しだけが血液、筋肉、神経などに存在しています。
カルシウムは骨や歯のイメージがあるかもしれませんが、元素の分類としてはアルカリ土類金属という金属の一種です。骨や歯のカルシウムはリン酸という別のミネラルと結合してリン酸カルシウムという形で沈着するのであまり金属らしくない見た目をしています。しかし、カルシウム単体の結晶は銀白色の光沢のある金属らしい見た目をしています。
カルシウムは生物の体内でさまざまな働きをするほか、金属として蓄電池や医薬品の製造、製鋼、建設用の材料などに幅広く使われています。カルシウムは我々の身近にある物質と言えるでしょう。
カルシウムの働き
カルシウムは骨や歯を作るのにたくさん使われています。体内にあるリン酸という別のミネラルと結合し、リン酸カルシウムとして骨や歯に存在しています。骨は新陳代謝を行い、一定期間内で骨形成と骨吸収を繰り返します。骨形成とは血液中のカルシウムを骨に沈着させ骨を再構築するはたらきのことで、骨吸収とは骨に蓄えられているカルシウムを血液中に溶出させるはたらきのことを指します。骨形成と骨吸収は体内中のカルシウムバランスを保つために必要なはたらきなのです。
特に成長期の子どもにはカルシウムは重要なミネラルです。身長を伸ばして丈夫な骨や歯を作るにはカルシウムが必要不可欠となります。昔から身長を伸ばしたい子どもは牛乳をたくさん飲んだりしますが、特定の食品だけからカルシウムを取ると栄養が偏るためあまり効果がありません。乳製品や野菜、小魚などからまんべんなく採ると効果的です。
その他にもカルシウムには出血時に血液の凝固を促したり、心筋の収縮作用を増して筋肉の興奮性を抑えたりする働きもあります。
カルシウムが不足するとどうなる?
カルシウムが不足すると血液中のカルシウム濃度が低くなります。すると体は血液中のカルシウムを補おうと、骨吸収をたくさん起こして濃度を保とうとします。すると、骨吸収で溶け出すカルシウムのほうが骨形成で沈着するカルシウムよりも多くなり、骨密度が低くなってしまいます。
この結果、幼児の場合は骨の発育障害が起こり、成長が悪くなってしまいます。また、高齢期、特に女性の場合は骨粗しょう症になりやすくなります。
また、骨に沈着しているカルシウムが血液中にたくさん溶け出している状態になると、細胞内や血管内にカルシウムが溜まり、動脈硬化や高血圧の原因となります。
カルシウムを摂り過ぎるとどうなる?
カルシウムを過剰に摂取すると便秘や高カルシウム血症、高カルシウム尿症、前立腺がんなどの病気になりやすくなります。しかし、これらの影響は摂取推奨量の数倍ものカルシウムを摂取しないと発生しません。
厚生労働省ではカルシウムの1日の耐容上限量を2,500mgと規定しています。これは牛乳に換算すると2リットル以上にもなるため、ごく普通の日本の食生活を送っていればこれだけの量を1日で摂取してしまう可能性はほとんどありません。
ただし、カルシウムが含まれたサプリメントを飲んでいる方は注意が必要です。サプリメントなら大量摂取が可能だからです。大量摂取したからといって必ず過剰摂取の症状が出るわけではありませんが、サプリメントを利用する際は用法用量や食事とのバランスを考えて利用しましょう。
カルシウムの摂取量
厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準2020年版」によれば、1日のカルシウムの摂取推奨量は、以下の通りです。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
| 18〜29歳 | 789mg | 661mg |
| 30〜49歳 | 738mg | 660mg |
| 50〜64歳 | 737mg | 667mg |
| 65〜74歳 | 769mg | 652mg |
| 75歳以上 | 720mg | 620mg |
【参考】厚生労働省:日本人の食事摂取基準
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
だいたい年齢と性別に応じて600mgから800mgの間ですが、これは牛乳に換算するとコップ3〜4杯程度です。カルシウムがたくさん含まれている他の食品もバランス良く摂取すれば推奨量を満たすのはそこまで難しくはありません。
カルシウムを多く含む食べ物
カルシウムを多く含む食べ物には、以下のようなものがあります。
| 乳製品 | チーズ、ヨーグルト、牛乳 |
| 魚介類 | 煮干し、わかさぎ、ししゃも、しらす |
| 豆類 | 大豆 |
| 野菜・海藻類 | こんぶ、モロヘイヤ、しそ |
【参考】文部科学省:食品成分データベース
https://fooddb.mext.go.jp/
カルシウムは加熱してもほとんど変化しないので、必ずしも生で食べる必要はありません。例えば市販の牛乳は加熱殺菌されていますが、カルシウムは問題なく含まれています。
カルシウムの吸収を助ける食べ物
せっかくカルシウムを多く含んだ食べ物を食べても、ビタミンDが不足していると吸収されにくくなります。結果としてカルシウムをたくさん摂取しているのにカルシウム不足になるといった事態になりかねません。
それを防止するにはビタミンDを多く含む食べ物も摂取して、カルシウムの吸収を促す必要があります。
ビタミンDが多く含まれている食品はたくさんありますが、代表的なものとして以下のような食品が挙げられます。特に魚介類に多いので積極的に摂取しましょう。
| 魚類 | 鮭、かつお、まぐろ、しまあじ、あんこう、しらす、にぼし、 いわし、にしん、きびなご、いかなご、など |
| きのこ類 | キクラゲ、まいたけ、など |
また、食物からの摂取以外にも日光に当たることでビタミンDの摂取ができます。特にお子さんの発育のためにも外で遊ぶことが有効です。環境省によると日光からビタミンDを摂取するには日光なら約15分、日陰なら約30分、両手の甲に日光が当たる程度で良いそうです。
【参考】紫外線環境保護マニュアル2008/環境省
http://www.env.go.jp/chemi/uv/uv_pdf/02.pdf
まとめ
カルシウムは骨や歯を構成するほか、体のさまざまな機能を維持するために不可欠なミネラルです。私たちの身の回りにカルシウムが含まれている食品はたくさんありますが、そのような食品を食べるだけでは不十分です。なぜなら、ビタミンDが不足するとカルシウムが吸収されにくくなるからです。バランス良く食べて適切にカルシウムを摂取しましょう。