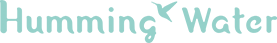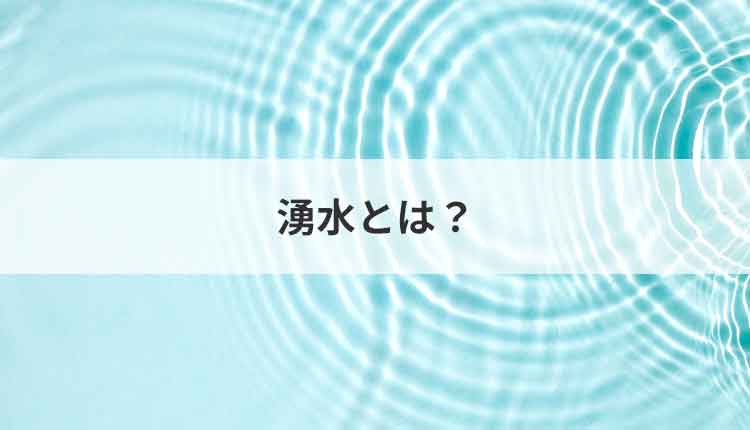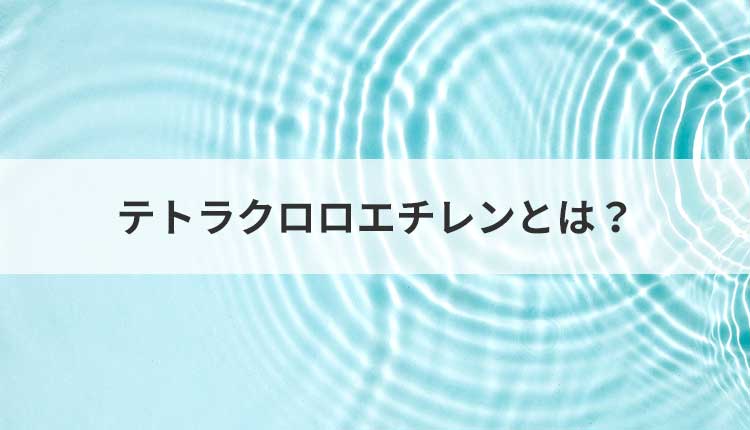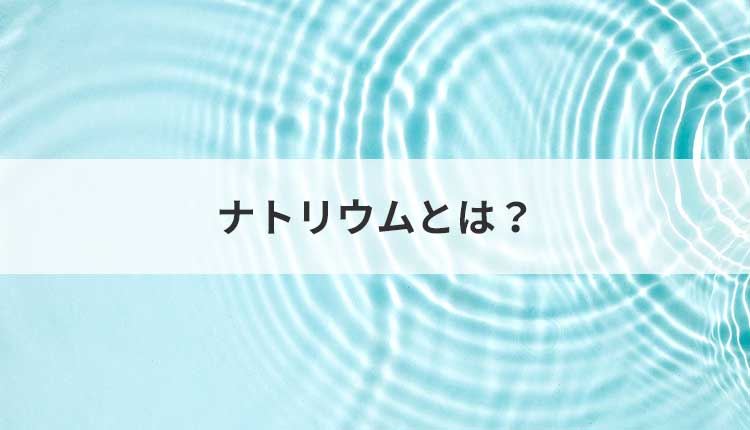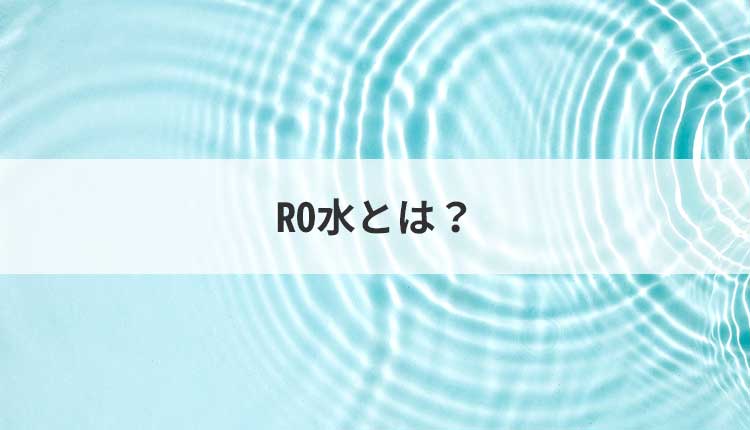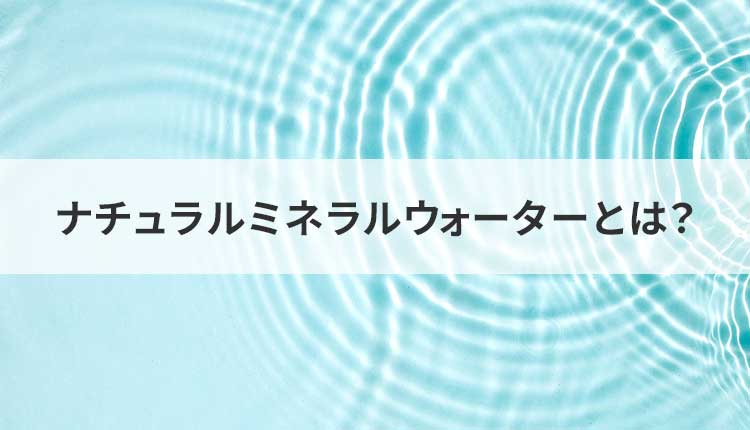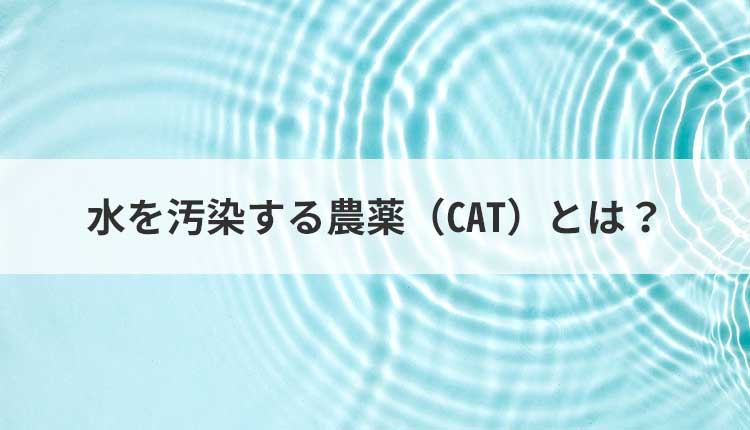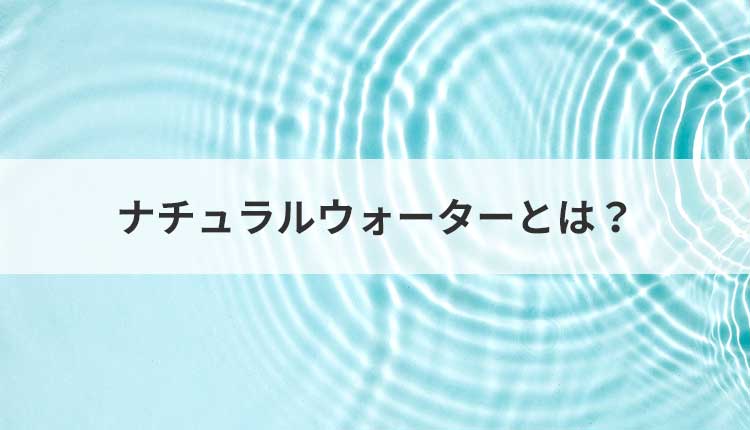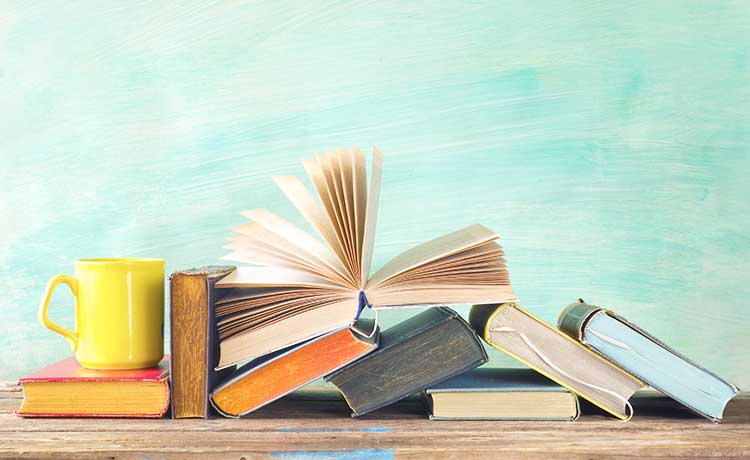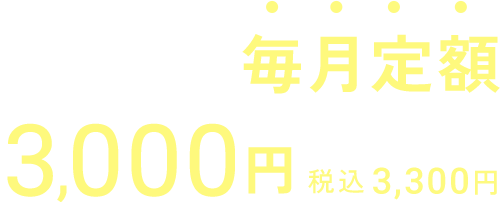日本全国、さまざまな地域で湧き出ている「湧水(湧き水)」。
古くから重要な水源として人々に活用され、湧水の周辺では文化や伝統が生まれました。
こちらの記事では湧水の定義などをわかりやすく紹介し、そのまま飲んでもいいのかという疑問や日本の湧水の名所などを詳しく解説します。
湧水について気になっている方は、最後までチェックしてみてください。
湧水とは?定義や特徴をチェック
まずは、湧水の定義や特徴、種類やタイプなどを詳しく紹介します。
湧水は地下水が自然に地表に湧き出る現象
湧水とは、「地下水が自然に地表に湧き出る現象」を指します。
昔から飲み水や農業用水、名産品の生産などさまざまなものに利用されてきて、現代でも重要な水源の1つです。
地下水から自然と湧き出たお水はすべて湧水の定義に当てはまりますが、これはとても広い定義になるため、さらに細かく分類分けすることができます。
種類やタイプについては、後ほど紹介していきます。
地形や地質、降水量などで水量や水質が変わる
湧水は地形や地質、降水量などの自然環境によって、水量や水質が変化するのが特徴です。
例えば火山地帯や山岳地帯では、雨水が地下まで浸透し地層を通る過程でミネラルを含むため、ミネラルが多く含まれたお水が湧き出ることが多いです。
ミネラルを多く含む湧水や水量の多い地域は、名水として有名な場所もあります。
環境省が選定している「名水百選」に選ばれている水源は、全国的に知名度が高いです。
古くから人々の生活に欠かせない存在
湧水は古くから人々の生活に欠かせない存在であり、地域の文化や伝統にも深く根付いています。
多くの地域では、湧水が神聖なものとされ、神社や寺院が建てられました。
また、お酒などの名産品も、湧水を利用して作り上げられたものが多いです。
さらに農村地帯では湧水を利用したシステムが発展し、農作物を育てるための基盤となってきました。
このように、文化や伝統が築かれた場所の中心に湧水があることは非常に多いです。
湧水やそれ以外の原水の種類をチェック
水道水や市販のミネラルウォーターなどには、湧水やポンプで汲み上げられたお水などが原水として使われています。
農林水産省が通達している「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」では、湧水に分類されるものとそれ以外の原水の種類と特徴が定められています。
こちらを元に湧水とはどのような特徴を持つのか確認してみましょう。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 浅井戸水 | ポンプなどを使用し浅井戸から採水した地下水 |
| 深井戸水 | ポンプなどを使用し深井戸から採水した地下水 |
| 湧水 | 水循環の過程で自然に地表に湧き出た地下水 |
| 鉱泉水 | 25℃未満で、溶け込んだミネラルなどにより特徴付けられる、自然に湧き出た地下水 |
| 温泉水 | 25℃以上の自然に湧き出た温かい地下水、または温泉法で定められたミネラルを含む地下水で飲用に適しているもの |
| 伏流水 | 川が透水層を流れる際に地中に浸透した水 |
| 鉱水 | ポンプなどで採水された地下水で、溶け込んだミネラルにより特徴付けられる地下水 |
湧水の定義は自然と湧き出たお水なので、ポンプを使用している井戸水や鉱水は湧水には分類されません。
対して、鉱泉水や温泉水は自然に湧き出るお水なので、広い意味では湧水に分類されます。その中でもミネラルが豊富なお水だということです。
地形によってもタイプが分けられる
湧水は、湧き出る場所の地形などの違いで7タイプに分けられるため、こちらも表にして紹介します。
こちらで紹介する7タイプは、地形や地質の条件が地下水の動きや湧水に影響を与えるため、湧水が湧きやすくなっています。
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 崖線(がいせん)タイプ | 台地や段丘の崖前面から湧き出たお水 |
| 谷頭(こくとう)タイプ | 馬蹄形や凸地形等の谷地形から湧き出たお水 |
| 湿地・池タイプ | 地下水が低い土地で湧き出し、湿地や池等を形成する |
| 扇端(せんたん)タイプ | 水の染み込みやすい扇状地扇端では伏流水が多く、それが湧き出したお水 |
| 火山タイプ | 溶岩流の積層や岩盤の割れ目を通る裂か水(れっかすい)や被圧地下水が自噴 |
| 傾斜丘陵地タイプ | 砂層と泥層が互層状態で傾斜または、被圧地下水が自噴 |
| その他 | 鍾乳洞など |
日本には上記のような特徴的な地形の場所が多数あるため、湧水が湧き出しやすい国といえます。
湧水はそのまま飲める?注意点や安全に飲む方法
湧水と聞くと新鮮でおいしいお水のように感じるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。ここからは、湧水を飲む場合の注意点や安全性について詳しく紹介します。
未殺菌のまま湧水を飲むのは危険
湧水は自然からの恵みである大切なお水ですが、未殺菌のまま飲むのはさまざまなリスクが伴います。
湧水には目に見えない細菌やウイルス、有害物質が含まれている可能性があり、これらが体内に入ると健康に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
特に免疫力が低い人やこども、妊婦などは気をつける必要がありますが、健康状態の人でも危険なのでそのまま飲まないようにしましょう。
湧水が飲めるかは自治体に確認
湧水を飲料水として利用する前に、まずは自治体にその湧水の安全性を確認することが重要です。
多くの自治体では湧水の水質検査を定期的に行っているため、飲料水として利用可能かどうかの情報を提供しています。
自治体のホームページをチェックしたり電話などで問い合わせしたりして、安心して飲めるか確認してみましょう。
水質的に飲める湧水なら煮沸やろ過してから飲む
自治体によって飲料水として認められている湧水であっても、より安全に飲むためには、煮沸やろ過してから飲むのがおすすめです。
煮沸やろ過することで、細菌やウイルスを殺菌したり不純物や有害物質を取り除いたりできます。
これらの処理を行えば、より安全でおいしい湧水を楽しむことができるでしょう。
日本全国の有名な湧水スポットとその特徴
日本には有名な湧水の名所が多数存在します。今回はそのうちの3つのスポットと特徴を紹介します。
北海道・羊蹄山(よいていざん)湧水群
北海道の羊蹄山は「蝦夷富士(えぞふじ)」とも呼ばれる美しい山で、その周辺には数多くの湧水スポットがあります。
ミネラル豊富でおいしいお水が豊富に湧き出ているため、連日多くの人がボトルにお水を汲みに訪れる場所です。
この地域の湧水は、雪解け水が地下に浸透し時間をかけてろ過されて湧き出るため、ミネラルをたっぷり含んでいます。
山梨県・忍野八海
山梨県の忍野八海は、富士山の湧水が地表に湧き出る8つの池から成り立っています。
この場所は「日本名水百選」にも選ばれており、透明度の高い美しいお水が湧き出ているのが特徴です。
各池にはそれぞれ神話や伝説があり、観光地としても人気があります。ここでは、各池の周りを散策しながら湧水の美しさを楽しむことができます。
また、近くの茶店では湧水で淹れたコーヒーを楽しめるのも魅力です。
京都府・貴船神社
京都の貴船神社は、水の神様を祀る神社として知られ、その境内には湧水が湧き出ています。
この湧水は参拝者が持ち帰ることもでき、地元の人々や観光客に親しまれています。
また貴船神社は四季折々の自然が美しく、特に紅葉の季節には多くの人々が訪れることで有名です。
水質は、石灰岩からカルシウムが溶け出していながら後味はまろやかで、おいしく飲むことができます。
湧水を飲むなら安全性に注意して楽しもう!
今回は、湧水の特徴や定義、種類などを詳しく紹介し、そのまま飲めるのかどうかも解説しました。
湧水は安全性が高いものの場合でも、煮沸殺菌などを行わずに飲むのは心配です。
日本全国、さまざまなエリアで湧水が有名な場所があります。湧水を飲む際は、安全性などを事前に確認するようにしましょう。
〈参考サイト〉
湧水とは|東京都環境局
湧水保全・復活ガイドライン|環境省
名水百選|環境省
ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン |農林水産省
(2024-7-9)