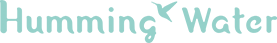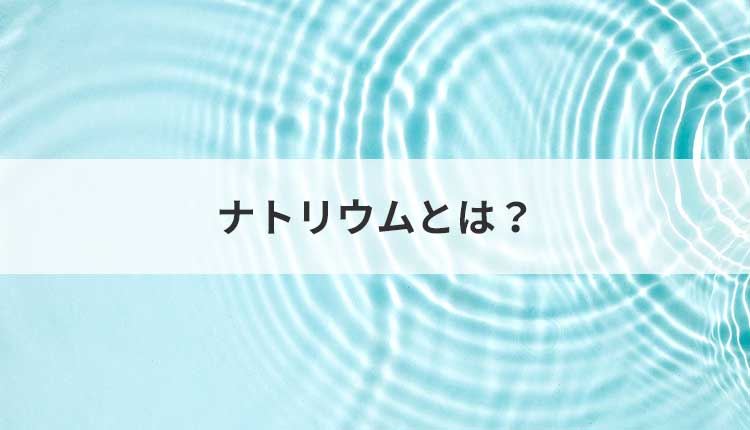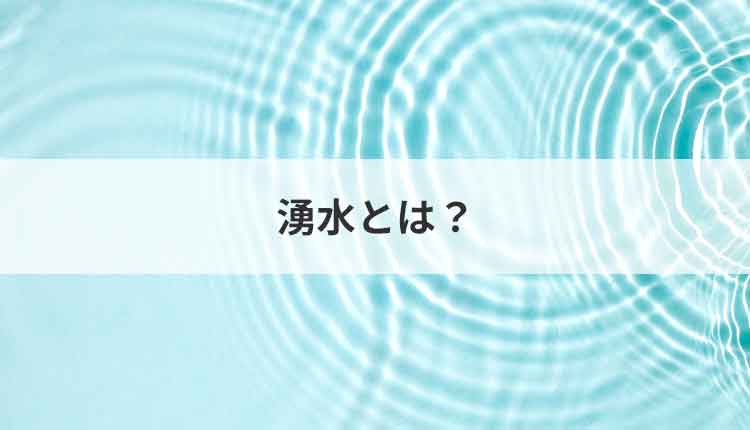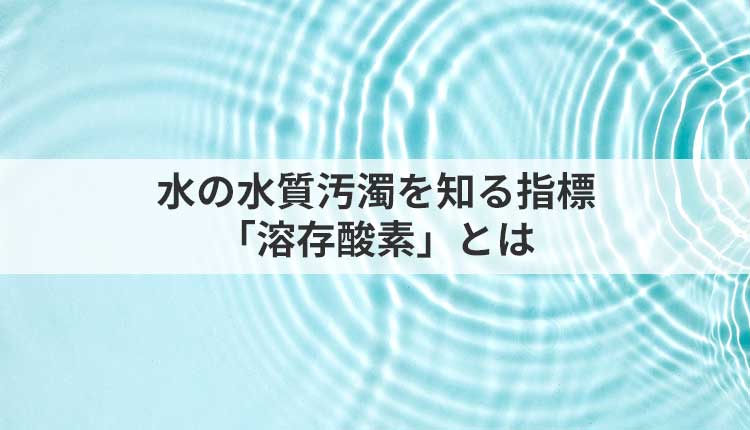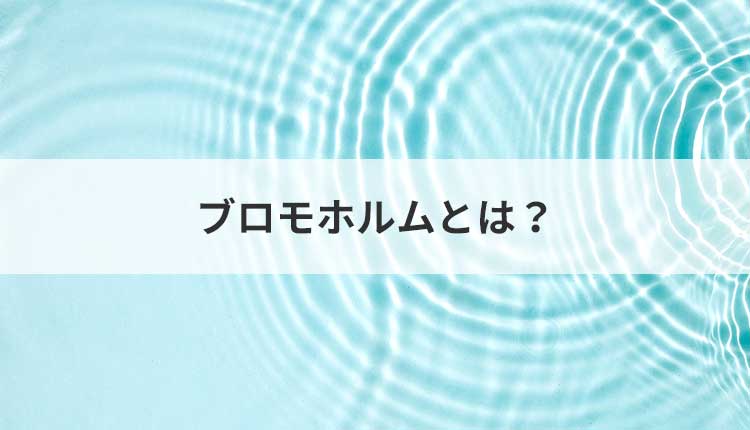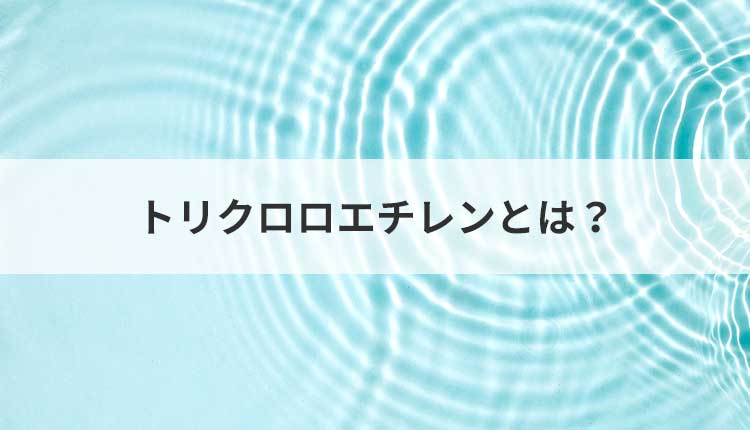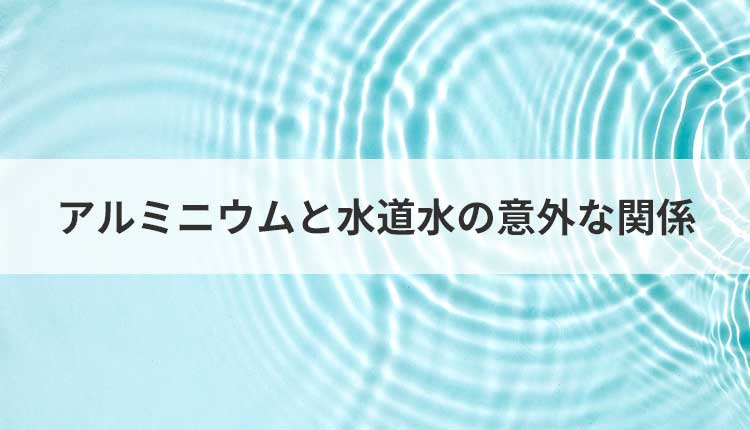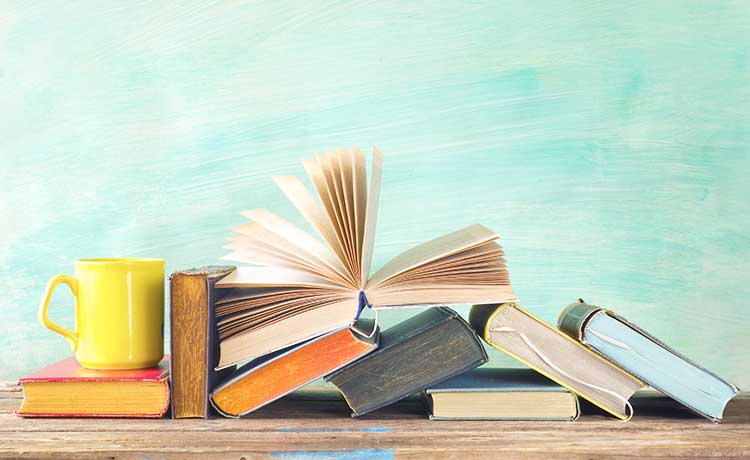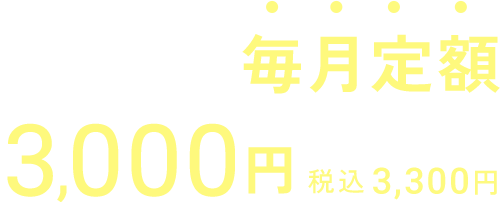ナトリウムとは?
ナトリウムとは人体に必要なミネラルの一種で、成人の体内に約100g含まれている元素です。体内にあるナトリウムのうち半分は細胞の外側にある細胞外液に、約4割が骨格に含まれており、残りは細胞内の細胞内液含まれています。
人間は必要なナトリウムの大部分を食塩から摂取します。ナトリウムの塩化物である塩化ナトリウムは単に食塩と呼ばれる場合が多いですが、塩化ナトリウムとは塩化物イオンとナトリウムイオンが結合したイオン結晶です。体に影響を与えるのは食塩全体の量ではなくナトリウムの量なので、食事からのナトリウム摂取量を考える場合には体に必要なナトリウム量から食塩の量を逆算するということが行われます。だいたい採るべきナトリウムのグラム数に2.54をかけ算した数値が採るべき食塩のグラム数と言われています。
ナトリウムの体内での働き
人間の体は摂取した水分やイオンとほぼ同じ量を排泄し、体内の水分やイオンの濃度を一定に保とうとする働きがあります。この働きにナトリウムが密接に関わっています。ナトリウムには細胞膜を通じて細胞の内側と外側にある体液のphやイオンなどの濃度を一定に保つ働きがあるのです。
また、筋肉を収縮させて動作させたり、神経に情報を伝達させたり、栄養素を吸収して全身に行き渡らせたり、血圧を適切に調節するといった体の機能にも関与しています。
1日に採ってもよいナトリウムの量
厚生労働省が公表している「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によれば、成人男女のナトリウムの食事摂取基準は、食塩相当量で1.5g/日です。ただ、1.5gは味噌汁1杯分程度の量であり、これを日本人の1日の基準とするのは非現実的であるため、男性は1日に7.5g未満、女性は6.5g未満が目標値とされています。
1.5gと比較するとずいぶん多いように感じますが、6.5〜7.5gとはラーメンやうどん1杯分くらいの量であり、日本人はこれを日常的に上回っている人が多いことに注意すべきです。
しかし、日本人の食文化に塩味は付きものであり、いきなり極端な減塩をしても食事が楽しめなくなってしまいます。例えば、野菜や豚肉など具沢山の味噌汁はカリウムや食物繊維、ビタミンを多く含むため、過剰なナトリウムの排出を促します。このようなナトリウム排出効果のある栄養素を上手く使って、無理なく減塩の食生活に変えていきましょう。
【参考】厚生労働省:日本人の食事摂取基準(2020 年版)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
ナトリウムが過剰に摂取されるとどうなる?
ナトリウムが過剰に摂取されると、細胞膜の浸透圧の関係で体内の水分量が多くなります。すると血圧が上がったり、体がむくんだりします。さらに、慢性的にナトリウムの過剰摂取が続くと、高血圧や胃がん、動脈硬化などの生活習慣病にかかりやすくなります。
ナトリウムが不足するとどうなる?
日本人の場合は平均的な食事と運動量で過ごしていれば、まずナトリウム不足にはなりません。ただし、激しい運動や肉体労働による多量の発汗や、食中毒などによる激しい下痢の場合は急激にナトリウムが排出されて欠乏する場合があります。ナトリウムが欠乏すると極度の疲労感、脱水症状、嘔吐を伴う食欲不振を引き起こします。
また、近年は夏の気温の上昇による熱中症が問題になっていますが、熱中症予防には水分だけでなくナトリウムも適切に摂取しないと低ナトリウム血症を引き起こす可能性があります。
ナトリウムが多く含まれる食品
最もナトリウムが多く含まれる食品といえば食塩です。特に岩塩などではなく化学的に精製した精製塩はグラム数のおよそ40%がナトリウムであり、ナトリウムの過剰摂取を防ぐにはまず減塩を心がける必要があります。
「出汁の素」にも食塩が多く含まれています。「出汁を利かせて塩味を補う」という減塩の工夫が紹介されていたりしますが「出汁の素」には塩分が入っているので注意が必要です。減塩の工夫をする際は食材から出汁を取りましょう。
調味料以外では、乾燥わかめ、塩から、漬物、魚の干物、塩昆布、インスタント麺、アンチョビ、煮干しなどに塩分が多く含まれています。
減塩の工夫
減塩の食事が良いとは言っても塩味が足りないと美味しくありませんよね。減塩の料理でも美味しくするコツは、塩味の代わりに他の味を上手く使うことにあります。
例えば「酸味」です。酸味は塩味を引き立たせる効果があるため、上手く料理に取り入れると少しの塩分量でも美味しく食べられます。
他にも「食材から出汁を取る」「コショウなどの香辛料を利かせる」「とろみをつける」「香味野菜をたくさん使う」などの工夫で美味しく減塩ができます。
ただ、自炊している場合はこれらの工夫ができますが、外食中心の場合はなかなかやりにくいと感じるでしょう。しかし、外食の場合でも工夫次第で塩分は減らせます。
例えば、ラーメン、うどんなどの麺類の汁に塩分が多く含まれるので、まずはこれらの汁を全部飲まないようにしましょう。次にコンビニや弁当屋などで購入した弁当に付いているソースやドレッシングは、かけないか、少しだけかけるようにすると塩分が減らせます。
また、ハムやソーセージなどの加工肉やちくわやかまぼこなどの練り物には塩分が多く含まれている傾向にありますので、これらはできるだけ控えめにしましょう。
まとめ
ナトリウムは健康に必要不可欠な栄養素です。しかし、摂取しすぎても体調を崩しますし、不足しても体調を崩します。塩分の濃い食べ物を控えたり、気温が高い場合は水分と一緒に適量を摂取したりするなど、適正量の摂取を心がけましょう。