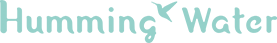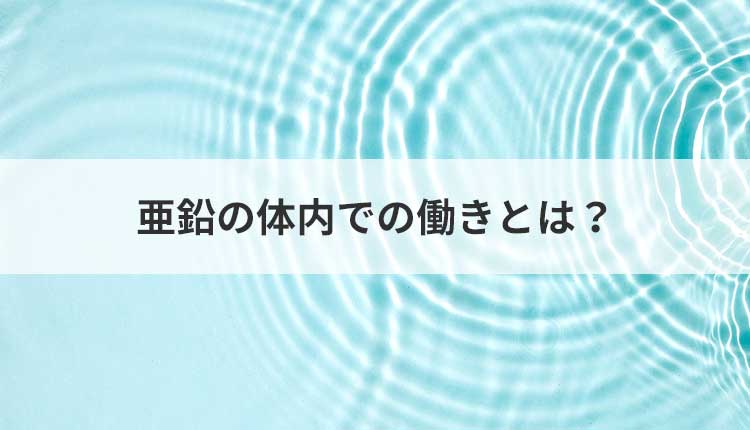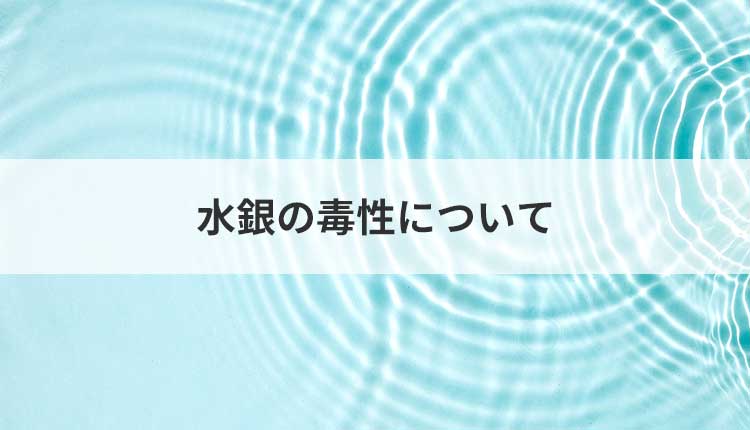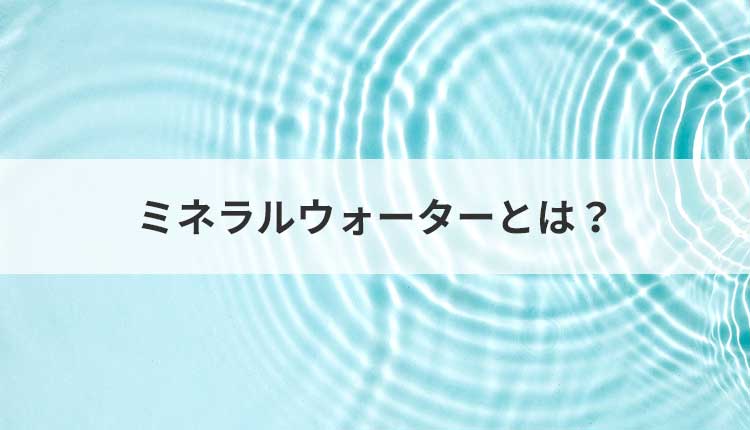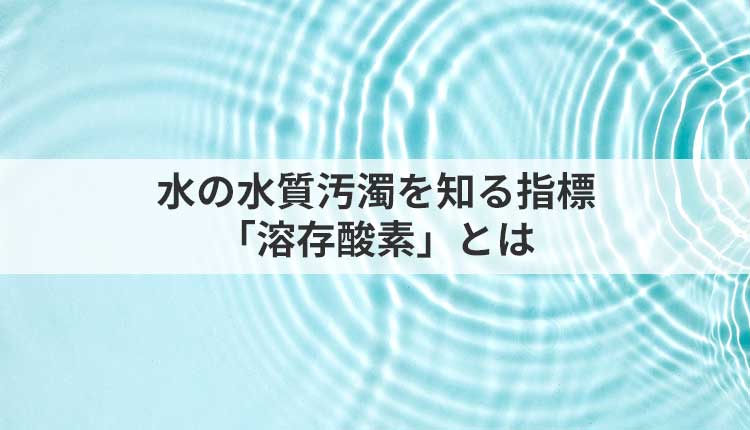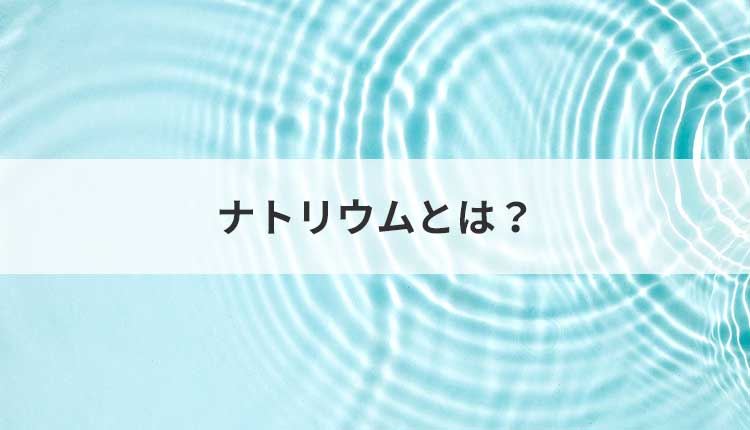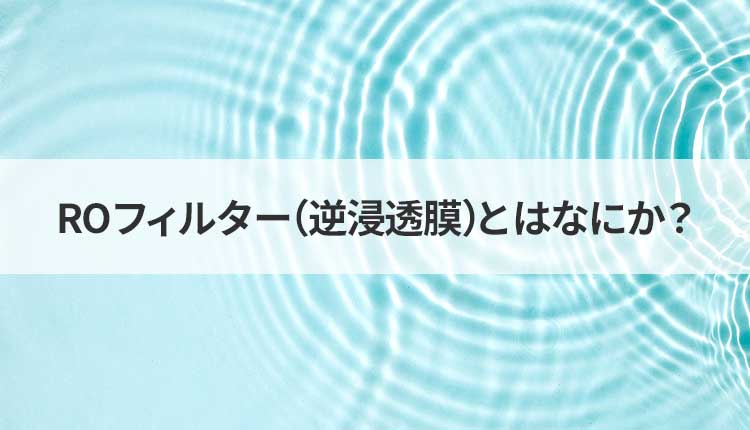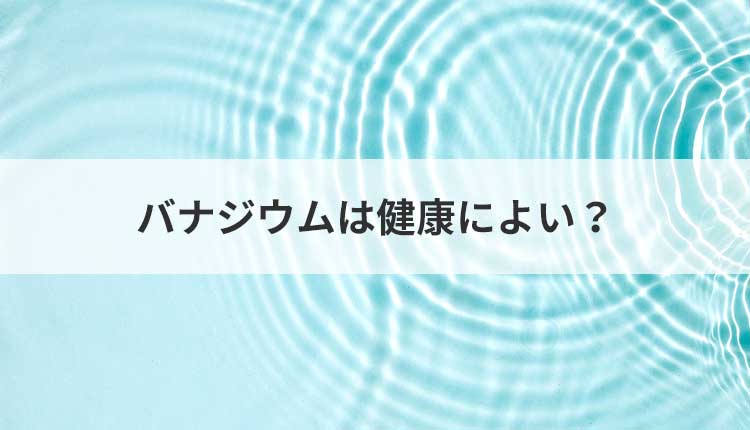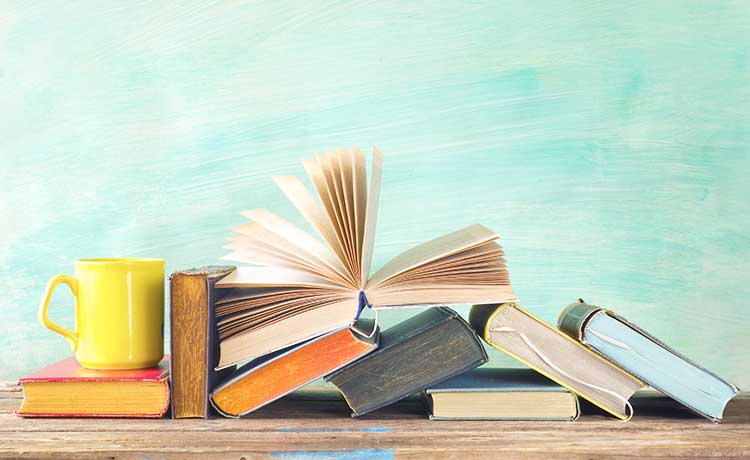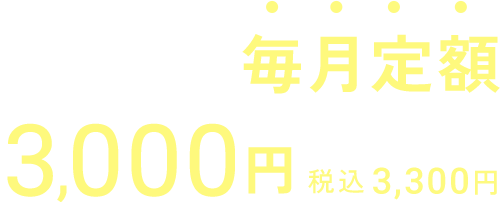亜鉛とは?
亜鉛の体内での働き
亜鉛とは健康の維持に必要なミネラルの1種で体内に2g〜4g程度含まれています。その多くは骨、筋肉、内臓など全身に存在し、体内のさまざまな機能を調整しているのです。亜鉛は体内の100〜300種類の酵素に関わっています。例えば、インスリンは亜鉛のサポートがあって効果的に働けます。亜鉛のおかげで糖尿病が防がれているのです。その他にも皮膚や髪の毛の健康、成長期の体づくり、アレルギーの抑制、妊娠時の母子の健康、怪我の回復、骨の形成など、その働きは多岐にわたります。亜鉛のおかげで全身の健康が維持できるのです。
水道水の中の亜鉛
通常であれば私たちが飲む水道水の中に亜鉛はごくわずかしか含まれません。水道水の中に亜鉛が増えると白濁して見えたり、金属のような味がしたりします。日本の水道水の水質基準では亜鉛とその化合物の含有量が1.0mg/L以下と定められています。これは耐容上限値よりも大幅に低いため、水道水の亜鉛の含有量が少しぐらい多くても健康にはほとんど影響は無いと考えられます。
亜鉛の推奨摂取量
厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準2020年版」によると、成人男性の亜鉛の推奨量は1日に11mg、成人女性の推奨量は8mgです。一方で、耐容上限量は成人男性で1日に40〜45mg、成人女性で30〜35mgとなっています。同じく厚生労働省が発表している「令和元年度国民健康・栄養調査結果」によると日本人の平均亜鉛摂取量は1日に8.4mgとなっており、推奨量に満たない量しか摂取できていない人が多い現状があります。したがって、健康維持のためには亜鉛を積極的に取るべきと言えますが、耐容上限量も定められているので、サプリなどで不自然に大量に摂取するのはやめたほうがいいでしょう。
【参考】
厚生労働省:日本人の食事摂取基準(2020 年版)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
厚生労働省:令和元年国民健康・栄養調査
https://www.mhlw.go.jp/content/000710991.pdf
亜鉛が不足するとどうなる?
亜鉛が不足すると、体の機能にさまざまな異常が出る場合があります。例えば、皮膚や髪の毛の異常。抜け毛が増えたり、肌が荒れたりします。他にも、味覚の異常や貧血、食欲不振、下痢、免疫機能低下などの原因となります。成長期の子どもの場合は体の成長にも影響が出る場合があります。
近年は若い女性を中心に亜鉛不足が原因とみられる症状を訴える人が増えており、過度なダイエットが原因と考えられます。ダイエットの際は亜鉛に限らず栄養バランス全体を崩さないよう、健康的なメニューを組むのが大事です。
亜鉛を過剰摂取するとどうなる?
亜鉛を過剰摂取した場合、短期的には吐き気、嘔吐、下痢、頭痛、胃けいれんなどの症状が出る場合があります。また、過剰摂取の状態が長期間続くと、貧血、免疫の異常、下痢、 HDL(善玉)コレステロールの低下などの症状が出る場合があります。現代の日本人の亜鉛摂取量の平均値は推奨量よりも低いため、日本人の平均的な食生活を送っていれば過剰摂取に陥るケースは少ないと言えます。ただし、サプリメントなどを大量に服用すると過剰摂取になる危険がありますので、通常の食事以外から亜鉛を摂取する際には注意が必要です。
亜鉛を多く含む食品
亜鉛は魚介類、穀類、肉類に多く含まれています。具体的には以下のような食品です。野菜類については魚介類や肉類ほど亜鉛は含まれていませんが、それでも少しは含まれています。
●魚介類
かき、かつお、サバ、いわし、いかなご、かたくちいわし
●穀類
小麦胚芽
●肉類
牛肉、豚肉
●その他
干しわらび、大豆、パン酵母、かぼちゃ、パルメザンチーズ、ココア、まいたけ、米ぬか
亜鉛の吸収を促進する食品と阻害する食品
亜鉛はクエン酸、ビタミンCや動物性タンパク質を合わせて摂ると吸収率が上がると言われています。一方で、亜鉛の吸収を阻害する食品もあります。それは、インスタント食品に使われているリン酸塩、練り物や加工肉に使われているポリリン酸、漬物に使われているフィチン酸などです。また、外食やコンビニの惣菜に使われているうまみ調味料(グルタミン酸ナトリウム)も亜鉛の吸収を阻害します。外食やコンビニの食品、加工食品をよく食べる人は動物性の食品を多く摂るなど亜鉛不足に陥らないように工夫したほうが良いでしょう。
まとめ
亜鉛は必要なミネラルですが、耐容上限値が決まっており、過剰摂取には注意する必要があります。通常の食生活ならば問題ありませんが、食事以外にサプリメントなどを服用している場合は用法用量をしっかり守りましょう。また、過度なダイエットや外食中心の生活は亜鉛が不足しやすいので栄養バランスが悪くならないよう工夫する必要があるでしょう。