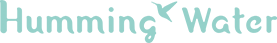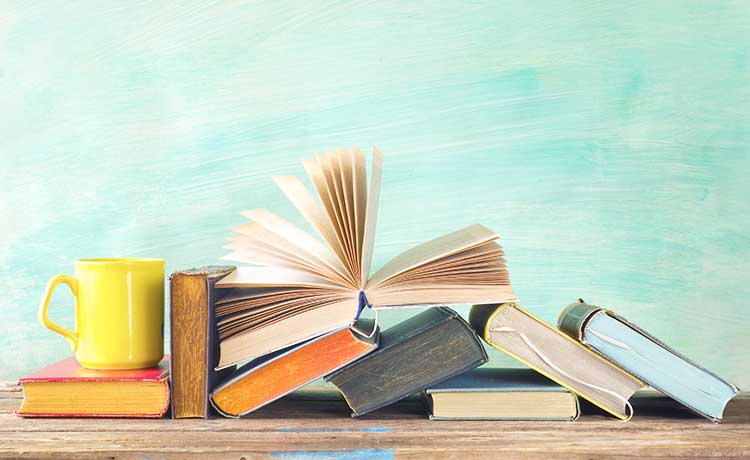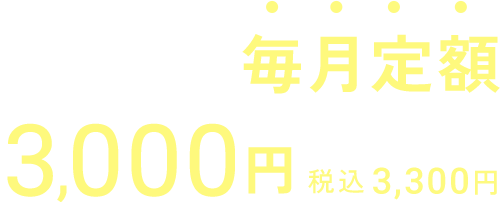宇治森徳 上薗みゆきさん/甘露園 田村千夏さん 特別インタビュー
【前編】
最近、いつお茶を飲みましたか?
忙しい中でも、お茶がそばにある暮らし。「ちょっといいな」と思いませんか?
もっと皆さまにおいしいお茶を楽しんでいただけるよう、お茶を知りつくす専門家のお二人に、「今さらなかなか聞けなかったお茶のアレコレ」をじっくりお伺いしました。

左:株式会社宇治森徳の上薗 みゆき(うえぞの・みゆき)さん。
日本茶インストラクターであり、茶審査技術七段の資格も持っておられます。
右:株式会社甘露園の代表取締役であり、日本茶を楽しむカフェなども経営されている田村 千夏(たむら・ちか)さん。
田村さんは、日本に2人しかいない女性日本茶鑑定士の1人です。
今回の【前編】では、上薗さんからお聞きしたお話をご紹介。お茶を楽しむためのファーストステップとして、キホンの「キ」から語っていただきました。
そもそも、お茶ってどんなもの?
ひとくちに「お茶」といっても、何をどこまで指すのか、あまり理解できていない気がします。
そうですね。お茶の定義はとても幅広いので、曖昧になってしまうのも無理はありません。
まず、皆さんがご存知の茶畑。そこにある、茶の木からとれる葉っぱで作られるのが「お茶」です。
緑茶、紅茶、烏龍(ウーロン)茶。これらは全部、多少の製造工程の違いはありますが、同じ茶の木から作られます。


「茶の木」って、正式名称なんですか?
生物学的には「カメリア・シネンシス」といいますが、正しい和名は「チャ」「チャノキ」です。
そうなんですね。今まで、チャノキは緑茶だけのイメージでした。紅茶や烏龍茶も元は同じなんですね。それなのに、味が全然違うのはなぜですか?
大きくは発酵させるか、させないかの違いです。
緑茶は、葉を摘んでからすぐに火を入れて発酵させない「不発酵茶」。
これに対して、烏龍茶は「半発酵茶」、紅茶は「全発酵茶」で、どちらも発酵させています。酵素の働きで色がついたり、独特の風味が生まれたりするんです。
チャノキからできるお茶以外にも、いろんなお茶があると思います。とうもろこし茶とか。
そういったものも確かにお茶ですが、チャノキ以外のものから生まれるお茶は「茶外茶(チャガイチャ)」と分類されています。
茶外茶の代表は、大麦を原料とした麦茶。玄米茶も、茶葉を使っているので緑茶ではありますが、炒った玄米をブレンドしているので茶外茶ともいえます。それから、近頃人気のルイボスティーは、ルイボスという植物から作られるものです。他にも蕎麦(そば)茶、昆布茶など、多種多様な茶外茶があります。
さらに、「緑茶」のカテゴリーの中にも、煎茶や番茶といった分類があるんですよね。混乱してしまいます…。
ざっくり整理しましょう(笑)。
おっしゃる通り、「緑茶」の中にもいくつか分類がありますが、身近なのは煎茶、番茶、ほうじ茶あたりでしょうか。
煎茶は茶葉を蒸して乾燥させたもので、緑茶の中で最も一般的です。
番茶は、成長した硬い葉を使った、低価格の気取らないお茶。
ほうじ茶は、煎茶や番茶を強火で焙煎して香ばしさを引き出したものです。茶色がかってはいますが、緑茶に含まれます。

また、ワンランク上の玉露という分類もあります。玉露は、日光を遮って栽培することでうまみを強めたお茶のことで、手間がかかるぶん価格も上がります。
玉露って、お茶の品種かと思っていました〜! 育て方の違いなんですね。
そうなんです。玉露になるお茶の品種には、あさひ、ごこうなど別の名前があります。
それから、緑茶は産地の気候風土に影響を受けて、さまざまに味わいが変わるのも奥深いんですよ。たとえば、鹿児島のお茶は甘みが強いですし、福岡のお茶はうまみ、静岡は渋み…。
私自身、宇治森徳に入社してから産地ごとのお茶の違いをすごく実感して、ますます面白さを感じるようになりました。

水出しとお湯出し、茶葉とティーバッグの違い
お茶の主な種類がわかったので、次は楽しみ方の知識もつけたいです。よく、スーパーなどで「水出し」できるティーバッグ入りの緑茶を見かけますが、お湯で淹れるのとはどう違うのでしょうか。
水出しは、甘みやうまみを好む人におすすめです。お湯出しよりもそういう成分がたくさん出るというわけではないのですが、水出しだと渋みや苦みが抑えられるので、結果的に甘みやうまみが強く感じられるのです。
あと、水出しにするとカフェインも出にくくなります。ゼロにはならないですが、寝る前に飲むお茶だけ水出しにするなど、工夫しても良いと思います。
ティーバッグタイプは、お湯出しの時にも便利に感じるのですが、使わないほうがいいですか?
お茶の葉は、乾燥した状態ではくるくる巻かれて長い針状になっています。それが、ふわっと開いていくときに味や香りが出てくるんですね。
ですから、ティーバッグに入れずにそのままの茶葉を使ったほうが、圧倒的においしくはなります。

ティーバッグに入れるために長い針をカットしたり、細かく砕いたりしているものは、味や香りが乏しくなっていることが多いです。
とはいえ、後始末のことも考えると、ものすごく便利なので、ティーバッグタイプを選ぶなら、ナイロンメッシュのような目の粗いものがおすすめですね。あるいは、葉っぱが膨らむ余地のある大きめサイズをおすすめします。
とても正直にいってしまうと、ちょっと頑張って高めのお値段のものを選べば、ティーバッグでも色や味がしっかり出ると思います。
何より大切なのが「お水」
お茶を淹れるのに使う「お水」についても、知っておいたほうがいいことがあれば。
お茶は99%以上がお水なので、お水がとても大事なんです!お水の味が、そのままお茶の味に影響するといっても過言ではありません。
日本のお水は、緑茶に合っているんですよね?
はい、日本のお水は緑茶に適した軟水です。
外国に多い硬水で、お茶の味を引き出すのは本当に難しいです。
以前、アメリカを訪れたとき、おいしいお茶を友人に味わってほしくて、お気に入りのお茶を持っていきました。現地で水出しにしたんですけど、丸一日置いても味が出なくて、泣く泣くあきらめたという経験があります。

では、日本でなら水道水をそのまま使っていいんでしょうか。
普段、水道水でお茶を淹れている人は多いと思いますが、正直おすすめしません。水道水はカルキ(次亜塩素酸カルシウム)臭があるので、お茶と反応して酸っぱいような、消毒液っぽい香りが発生しがちです。
もし水道水を使うなら、10分程度しっかり沸騰させるとカルキ臭を減らすことができます。ただ、すべての不純物を除去できるわけではありませんので、なるべく水道水を使用する場合は、ハミングウォーターのような浄水したおいしいお水で淹れるのがいいと思います。